

|
 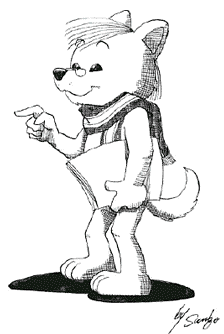 |
(八) リハーサルの日々 それから数十日がたちまして、初秋の風が吹き始めるころになっていました。 芝居の練習は、店を閉めた後のウサギさん花屋の裏庭で始められていましたが、皆がいっぺんに集まることは中々出来ませんでした。仕事があったり、使いで東北の山に出かけるものがいたりして、どうしても揃わないのです。それに台詞を憶えているものや、まるで自分の役が判っていないものがバラバラで、どうも練習がうまくはかどらないようでした。 そんな、ある日、ギンジロさんがいつもより早く「ロレットット」にやってきました。客もまだ犬のケンタ君だけで、静かなものです。ギンジロさんはカウンターに座ると、長髪の立て髪を分けながら、 「親父さん、ケンタ君、実に済まないが僕は演出家を降ろさせてもらうよ。」 こんなことを突然、言いだしました。 「えっ、またどうして。」 ケンタとキジ親父は目をパチクリさせて驚きました。 「どうも言いづらいんだが、実はね、こちらの芝居の頃に、丁度、角砂糖劇団の公演がきまってしまってねぇ、こちらの方もやりたいんだが、あちらの芝居もチャンスだしね、そうなると練習やらで、どうもこちらの芝居を手伝っていられないんだよ。」 最近、本物の芝居の仕事の無かったギンジロさんの身の上を考えたら、この申し出も仕方ない事だと、ケンタもキジ親父も思いました。ギンジロはすまなさそうに羽根をすぼめると、 「もっと、早く言いだせば良かったのだが、つい言いずらくてね。せっかくここまできたのに残念だけど、もし、何か手伝えることがあれば、なんでもするからね。」 そう、言い残して帰って行きました。 すると、今度はキンジロさんと入れ違いにサルのコウタラ・イッキとイノシシのエンコ・トトリが揃って入ってきましたが、この二匹も何か気まずそうにしています。 「どうしたの。何かあったの。」 キジ親父にこう尋ねられると、二匹はお互いの顔を見合わせながらモジモジしていましたが、やがてサルのコウタラが思い切ったように口を開きました。 「実は、良く考えたのだけど、僕たちには芝居は無理だと思いましたね。そこで、ひとつお願いがあってきたのですが、僕たちは今回、降ろさせてもらいたいのです。」 「なんだって、君たちまでが。又それはどうしてだい。」 ケンタが言葉を荒くして言いますと、 「秋の仕事が忙しくて、どうも一つ・・・。」 イノシシのエンコが答えました。 「だから、いつも皆の仕事が終わってから練習してるんじゃないか。」 「そうだけど、僕はいつも参加してるけど、どうも台詞は少ないし・・・」 サルのコウタラがこう言ったときです。 「この、馬鹿ザル!」突然、キジ親父が怒りだしました。 「台詞が少ないので、止めたい、本当の理由はそうなんだろう。」 「そ、そんな事は言ってませんよ。本当に仕事の方が、」 「嘘つけ、お前達はいつもここに来ては、ああ仕事ばかりで面白くないな、何か皆で愉快なことをしたいなと言ってたくせに。それにじゃあ、何だ。僕だってね、台詞はヒエエイーだけだぞ。それでもそれをどんなふうに言おうかと毎日、工夫しているじゃないか。」 すると、サルのコウタラが口をとんがらせながら言いました。 「親父さんはいいよ、それでも殿様の役だもの。僕なんて男なのに女の格好をさせられたうえに台詞と言えば、何かと親父に向って、御機嫌はいかがでござりますか、こればっかりだもの。すると親父はヒエエイーって叫ぶけど、僕はその時どうしたらいいかと、もうかっこわるくて嫌になっちゃったんだ。」 「じゃ、役を変わってやるよ。」 キジ親父は、これを聞くと言いました。 「まあまあ、ちょっと待ってくださいよ。」 先程から話を聞いていた、ケンタが言いました。 「コウタラさん、まだ練習が始まったばかりじゃないですか。本も変わって行くし、台詞ももっともっと増えるだろうし、それにこれは楽しみながらやろうということで始まったのですよ。あれじゃ、いやだ、これじゃあ、いやだ、と言うのではなくて、皆が楽しむために始まった話じゃないですか。」 「じゃあ、言いますけど、」 それまで黙っていたイノシシのエンコが鼻息もも荒くして口を開きました。 「ケンタさんの言うことはわかりますが、霧の精になったカエルのアサケなんか、もうあっちでもこっちでも自分の役の事を言い触らして歩いていて、私がほとんど主役ねなんて言ってるんですよ。私の付人に二人の腰元がいるんだけど、これがイノシシのエンコとサルのコウタロがやるの。お似合いね、なんて言ってるものだから、私が森を歩いていると皆が馬鹿にするんですよ。どこが一体、皆で楽しむ芝居なんですか。もうこんなのよしましょう。」 エンコは本当に怒っているようでした。 こんな具合でしたから、キジ親父は怒りだし、ケンタはあきれるし、二匹も中々心にたまった不満が溶けそうにありませんでした。今日の所は、何とか説得して二匹を帰らせましたが、 「あの二人は、止めるかもしれないね。」 ポツリとケンタが言いました。 「まったく、話にもなんない。もうそうなったらこの店にも来させないから。」 キジ親父はそう言うと、がっかりと肩を落しました。 演出家のギンジロが降りることになった話から始まって、このような話は次々に起こってきたのです。 実際に秋の仕事が忙しくなってしまった者は仕方無ないとして、ある者は台詞のことで、ある者は芝居の熱がさめてしまい、理由はどうあれ劇団作りの話なんぞは現実の生活から眺めたら所詮、真夏の夜の酒の上の物語にしておけば、それでいいじゃないか、こう言う気持ちが秋風とともに皆の心に吹いてきたのです。 こうなると次第次第に、皆は練習に来なくなり、居酒屋「ロレットット」に足を運ぶ動物達も少なくなっていきました。秋風が本当に楓路地の暖簾を吹き過ぎていったのであります。 |
|
|
|
|
|