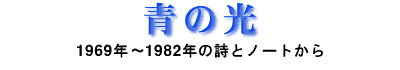
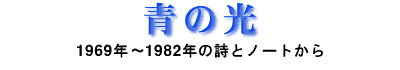 |
目次 1 架空のオペラ(1969年のノートから) 2 毒薬と狂気(1970年) 3 木蓮幻想 4 エレジイ 女へ(1971年) 5 雑記蝶 6 如来の華 |
|
木蓮幻想 |
| 老婆がただ独りで住む広大な屋敷の庭隅には、旧家の歴史を刻むように、一本の木蓮の大樹が聳えていた。 春ともなると、屋敷中に隠微な幻香を漂わせて、木は純白な花を結ぶ。その香にも又、根深い歴史の皺が彫られている。 気品に満ちた老婆であったが、浴室を嫌い、木蓮が咲く頃ともなるとその大樹の下で行水をするのを好んだ。もっともその習慣は、老婆がすべてを失った後からのことである。財産も地位 も、そして夫や愛しい息子を先の大戦で失い、広大な屋敷と老婆の気位だけが残ってからのことである。 老婆にとって、木蓮の下の湯浴は彼女に残された唯一のお転婆であり、娘時代にうえられた性格への冒険であった。そして木蓮の大樹だけが、その輝かしい時代を象徴するかのように、今も昔と変らない威風を残しているのであった。老婆の肌は木蓮の沈黙を映して、初夏の夕暮れの中で、まだ光沢を失わずに居る。風に渦巻く湯気の中で、老婆自身はまだ桃色だ。 ある宵、悪戯な瞳を輝かしていた魚屋の小僧は、老婆の肩から流れる白い湯気に溶ける木蓮の芳香にむせて、木塀の穴から離れる。と、そのせつな、小僧は自分の首筋を何者かの放った鋭利な光ものでグサッとえぐられた。小僧の「あっ痛。」という碁へ叫び声よりも早く、一匹の見事な白毛の猫は、魚を食わえたまま小僧の首筋を飛んで、木塀の上に居た。 それから、ギロリ、 小僧を睨んだかと思うと、ヒラリと裡に消えた。 木蓮の根本に舞い降りた泥棒キャットと老婆の目があった。老婆の裸身は、彼の瞳の異様な輝きに、処女のように火照た。 ・・・私ハ舞踏会ノ夜、アノ方ノ瞳ニ見ツメラレタノヲ、又、思イ出ス・・・。 この夜以来、老婆はこの不敵な愛しんだ。それから、その首を愛撫しながら、他人の食に施されてはならない、盗みもならないと教えを垂れた。こうして猫は広大な屋敷の中で、老婆の従順な帝王になった。 春、夏、秋、冬、そして春は巡った。すると初めて木蓮が花を結ばなかった。老婆にも湯浴みする気力が急に失せて行った。 又、四季は巡った。老婆は今や、床の中から障子を透かして花の咲かなくなった木蓮を眺めやるばかりであった。木蓮はいたずらに伸びた枝を、春風に笑わせている。老婆は寂しそうに猫の頭を撫でながら、寿命を思う。以前にまして色艶が雪のような白さに輝いて来た猫の毛並を、今は斑点に茶色く錆びた老婆の手の甲で何度もさ擦りながら。 翌年の春、老婆は木蓮の枯れ枝を見つめながら、息を引き取った。早春の風が、夜空に懸かる三日月を冷たく震わせる夜である。青く光が、縁側を舐めた。すると、老婆の死臭の傍らから雪のように白いものが、糸を曳いて、突然庭の青い水底のような空気の中に飛んだ。そして、木蓮の根本まで駆けると、白い生き物は伸びた爪でそこの地面 を掘り出した。するとやがて、土の中からは、頭ばかりがまだ腐っていない一匹の魚・・・あの魚屋の小僧から盗んだ鯖の・・・死骸が出てきたのである。 早春の風は、ヒッユと吹いて、冬の季節の尾鰭を切った。 と、そこにあった魚の白骨が、頭だけを残して、サラサラと硅石のように崩れ、折りからの青い光の中を静かに木蓮の枯れ枝に沿って舞い上がった。 魚の頭を齧ると、猫は去った。その行く得は知れない。老婆の居なくなった広大な屋敷の庭に、村人があの隠微な幻香を放つ木蓮の白い僚乱をふたたび見たのは、その後のことである。 |
|
|