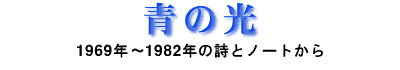
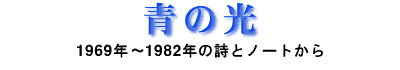 |
目次 1 架空のオペラ(1969年のノートから) 2 毒薬と狂気(1970年) 3 木蓮幻想 4 エレジイ 女へ(1971年) 5 雑記蝶 6 如来の華 |
|
如来の華 紫陽花 濡れそぼる六月の雨の下 傘を持たないぼくは 君の濡れた紫を、愛でよう。 * 百合 ぼくは、いつも 君の小首を傾けた 正しい視線を受ける * すみれ この都会の五月の夕べ 無機質な壁に照り映える ぼくをおびやかす 光の塊の羅列 それでは皆さん、さようなら 明日から、ぼくは円くなります。 * 宵待ち草 灰色の夕暮れに、 天体望遠鏡を買い求め オレンジ色の月を眺めるのは、いいことですが その昔、住んでいたという兎も、今は行方不明で 都会の電極層に捜索願いが貼られています。 誰か、あの兎の行く先を教えてください。 ああ、ひとつだけ手がかりはあります 月の兎は金色に輝く宝石箱のような眼をしてましたから、 こんな季節の灰色の夜でも、きっとその瞳はどこか光っているはずです。 逆さまに覗いても、まあるくて、もうきっとキラキラと映るはずですから どうか、あの兎を見つけたら、ぼくたちは灰色の時を変えて すきとおった伝説の季節に立ち帰りたいものです。 * 如来の華 バビロンの庭園に、ダクダクと僕は 400ccのバイクを駆って 東洋の一輪の睡蓮を、届けよう。 (実に白きその花は、昨日、山の麓から採ってきたのです。) あの方の、光る素足を浸した泉に、 薄暮の安らぎが訪れた時に生まれた誓いの花よ 今や街はむっつりとふやけ、デコボコして 透明なエーテルはもう真空地帯に帰ってしまいましたから この花から立ち昇る濃度100%の芳醇な香気が必要です。 (実に白きその花は、昨日、山の麓から採ってきたのです。) あの方の、疲れに澄んだ瞳が閉じられて 冥想の泉に浮かび上がった、幻の花よ。ー雲が晴れていくよ ー風が運ぶんだよ ー雨も静かに去って行くね 僕はバイクの背にもたれ、立ち昇るエーテル達の声を聞く この千九百八十年のバビロンが 砂崩れする音を聞きながら 僕は自分が走ってきた高速道路が、タイヤの跡をもうとどめないのを知っている 音もない、光もない世界。 しかし尚 それらよりも早く、確かな香を放つ夢幻の花よ。 (実に白きその花は、昨日、山の麓から採ってきたのです。 * 苦しみの声 僕は貧乏なんかに負けてしまう 弱い心を持っているので 心までが倒産してしまいそうだ。 例えば、雨が泣く、そこで滑べって終わりだ。 例えば、酒だけは求め酔い、それで勝ったつもりだ。 例えば、花を見て、惨めに染まる。 ああ、だがこれは僕の心の呪われた宿命であり その自らを転換するために、そんな雨や酒や花があるのだ。 貧乏を、誰のせいにするでもなく 自らを強くしてくれるための財産なのだと思える 毎日の真摯な働きと、人を侮辱しない気持ちと 丸い頭脳と、四角い心臓をとを持って 温かい心で、優しく人を見よう。 そして、強く自分に信念を祈ろう ホラ、雨は紫に煙り、酒は美神を招き 花は口づけを与えてくれる そのようにしかないものなのだ だからもう、僕をひとり解き放ち 皆のために、皆のために、 この貧乏から得た宝を 分かちあう時が来ている。 物質と形象に染まることなく、汚れずに来た、 深い底からの声があるではないか。 その声を失った時こそ、僕は生きていながら死んでいる、 本当の貧乏人だ。 * 確信 ー岡本君に 確かなる信頼は、物質よりも豊饒な、存在する光である。 確かなる信頼は、精神よりも澄み切った光である。 だが、この光は中々目に見えないので、 それ故にいつも、時代の詩を生む原石のままである。 例えば、これは詩ではあるまいが、 小林秀雄はこう言った。 「命の力には、外的偶然をやがて 内的必然と感ずる能力が備わっているものだ。」 この能力とは、それは生命の無始無終にある光の発見へのエネルギーであろう。 なんと勇気づけられる光であろうか。 そのような光を見た者達まだ本当に少ないのだ。 おのれの種を、人のための果実にすることが出来た人が本当に居ただろうか。 おのれの結果を人のせいにしたことはあっても、 おのれの原因を人のせいにしたことはあっても、 そのもっと遠くにある自分という命の種を、自らの中に求めなければ、 それは花でもない、果実でもない。 この確固たる主観を抜きにして、客観とは唯の抽象でしかないだろう。 それを現実だなどと呼ぶのは止めよう。 あの光が、もう君の心の中から消えることはあるまい、 それを確信と呼ぼう。 * 夜の雷 十一月の雷が鳴っている。 何の音か、この雨に、 ・・・ああ、慰めだと思い、 ドラム、ドラムを鳴らせ。 何の光の絵か、この夜に、 ・・・ああ、独りぼっちだと思い、 スケッチ、スケッチ描きなぐれ。 十一月の僕が震えている。 何の酒か、この部屋で、 ・・・ああ、この酔いのために、 ユーラリ、ユーラリ人を責め 何の夢か、この言葉に、 ・・・ああ、この夜が、 コト、コト無情だ と唄うのか。 (かくも弱く、僕は天空に身を委ね、裸のままの交信をする。) 十一月の雷が鳴っている。 叩け、叩け、叩き終わって、 光を躍らせろ。 * |
|
|