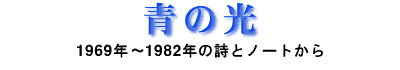
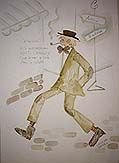 |
田村セツコ氏が贈ってくれた僕の肖像画 絵をクリックして全体を見てください |
| 序 | |
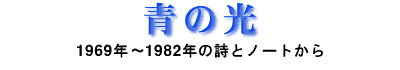
|
|||||||||
| 昔の原稿がひと束、どっさりと押入の底に眠っていた。
今からおよそ二十五年前、二十歳ぐらいから書き始めて、それから二十七歳ぐらいの間までに書き溜めておいたものである。 たまには日干しもせねばと、取り出して読み返してみると、虫に食われるのも当り前のように稚拙で恥ずかしい若芽作りのものばかりであったが、そのまま陽の目に晒してみたのが、今回の小冊子になったのである。 思えば、昔に踊った創作欲の光は、質を同じにはしないが今も僕の生活の合間を縫って、心の中を照し出す。こんな繰り返しがこれからも続くのだろうかと思うが、光はやがて心の中よりも生活そのものになるようにと、 直に照り映えるのかも知れない。そうなれれば、このように深く眠っていた原稿を今更に、人目に晒けだすような事をしないでも済むのかも知れないのだが。 僕だって食い物は旬な内に出されるのが旨いと言うことは知っているつもりだ。 ところが、一昨年、やっと思い立ち自分の童話集を自費出版したのだが、その中の幾編はやはりその昔に書いた物であった。誰に読んで貰えるものか、人目に晒すことなどないだろうと思っていたそれらの作品が、いざ本と言う形態となってみると、やはりその体験は止み難い魅力であった。そこで今回は、童話以外の詩や散文をまとめて、やはり自費出版の道をとり ・・・それ以外の手だて等あるわけないので・・・「青の光」と題を付けてみたのである。まさか過去の「排泄物」という題を付けて出版するのも忍び難く、だが、内容はその程度だなと、今は思っている。 1992・12・8記 |
目次 1 架空のオペラ(1969年のノートから) 2 毒薬と狂気(1970年) 3 木蓮幻想 4 エレジイ 女へ(1971年) 5 雑記蝶 6 如来の華 |
|
「架空のオペラ」(1969年のノートから) 流れ去る冬の朝日は皆、鏡の中に消えてしまった。 今朝、女がこんなに美しいのも、そのためだ。 * 冬の河、火照る頬、染み入る霙、泣き濡れた女 とシャーベット。 * 詩人の言うごとく、人は遠きにありて故郷を思うものらしい。 だからぼくは東京を離れたのだ。 だが、離れれば離れるほど、東京はぼくの享楽地帯であった。 * 空虚さは募るばかりであった。 二十一歳のぼくの心には静かな海と嵐があった。 ぼくは右を見て笑い、左を見て笑った。 * 唐突に、女が口を開いた。 細い絵筆が白い指先から伸びて、カンバスの水面を流している。 「帰ろうと思うの、私、東京へ」 「帰るですって?」 少年は驚いて、年上の女を振り向いた。 ぼくの記憶の中にある利根川での光景。月に誘われて、 月見草が咲き乱れていたっけ。 ぼくはあの日から「喪失」を恐れた。 * 蜻蛉 白壁に青い魚の瞳が映える夕暮れ 風は抜け、匂って来たものは 河原の軽石を掠めた蜻蛉の恋 空を切る竹竿の先には母の声 山、黒く 陽は、向こうの橋を 隣の町へと渡って行く * 居ながらにして自己を無にすること、これこそがぼくの覚えた復讐だ。 * 悲しみを逆説に言うなんて馬鹿げた仕業だ。 真の悲しみを表現するには二重のアイロニーが必要だ。 つまり「悲しみ」を「悲しみ」と直接に言い得ることが、 真の悲しみである。太宰治を心情的に理解したと思っている奴ら。 太宰は正面切って悲しい心情を文字に書いた。 彼は二重のアイロニを持っていたから、彼ほど下手な嘘つきはいなかった。 道化以上の正直者。 * 僕の好きなジャズ。それはヨーグルトのブルース。唾がでる。 * 声 いつでも涙は用意されていた 素直な声を聴くためにだけ 煙草に煙る部屋の中に座りながら、僕は しかし、青空を映した窓辺なんかに 訪れはなかった 昼間の花々、土の香りの苦さばかりで 暗くも、澄んだ声の光など 風は窓を叩くことを忘れ ぼくは只、雲の流れを見つめていた 遠い天使の投げた矢の跡を追いながら * アバンギャルド等という衣装を纏って、今日を闊歩しているコンプレックス野郎共。 口を揃えて・・・ 「礼節?フン、堅苦しい。」 「ロマン? フン、甘い、甘い。」 「感傷? フン、女々しい。」 「当節、そんなの古い、古い。」流行に反逆するべきだ。 人々が恥ずかしがる言葉とは確かにある。 その時こそ、ぼくは大いなるノスタルジックの抱擁者でありたい。 * どうやら、ぼくの心には髪喰い虫がいるらしい。 白かった紙が茶色くなってきたので、奴らは 益々俺の心の障子を大きく食い破る。喰いやすいからだ。 * 穴の空いたバケツが、光のつかぬ 電球玉と言い争った。 「なんて様だ。」 嘲笑、これほど又、嘲笑される性格を持った笑いはない。 * メフィストフェレスが言った。 「ドストエフスキーって野郎、あいつは生きてるファーストだ。」 又、言った。 「チェーホフって野郎、あいつは死んでるファーストだ。」 又、雨のそぼふる日、彼が窓辺にやってきた。 「どうした、メフィスト。悪魔もしょげるかい?」 彼はキッとぼくを睨めつけ、真顔で言ったものだ。 「人間て奴はね、君、悪魔以上の悪魔だ。」 * 横這いを拒否して、気違いと呼ばれた一匹の蟹が、ある月の夜の海辺で、 濡れて輝く桜貝の上に そっと、しょっぱい涙を落した。 「これなら、誰もわかるまい。」 * 海・・・・ 海は涙の集まり。人は一度は訪れて、涙を忘れて行く。 * 尾道の旅 海が燃えている小島の花祭り 雲に湧き、風ちぎる 色とりどりの沖の旗 私は白壁の葉紋に寄り 紫の心を取り戻す 鳴呼、「陶酔」の美が欲しい。「素面 」の醜が欲しい。 「美」は冷徹だ。素面でやって来て、僕達人間の甘えた感傷も、痛烈な批評も、 果ては賛辞をも、何ひとつ受け入れない。 * 芥川龍之介、彼は明治の産み落とした私生児であり、昭和に死に行く異邦人だった。 そして、いつの世にも完成者であった。これからも。 小林秀雄、彼ほど出発に際し芥川を意識した芸術家はいなかったろう。 彼の著した「志賀直哉」「ランボウ」等は呼とことごとく芥川の屍の上に立脚している。 彼は芥川に関し僅か数枚の評論「美神と宿命」しか書かなかった。 人間は最も意識すべき人間を唾棄する。 * 行動の中に理論がないのが嫌いだ。 理論の中に溌剌たる行動の息吹のないのも同様である。 そして何よりも理論の中には一抹の灼熱の情熱を孕み、 情熱の中に一抹の鋭利な理論を持つことだ。 詭弁とは上げたり下げたり、右往左往、 畢竟自己の独裁を成し遂げようとする言葉の不誠実。 右翼洗礼者の落し穴。 平穏の裡にこそ最大の不幸が埋もれているとは確かにその通りだ。 光を求めて飛んでくる夏虫を、一撃の許に、人間は何わぬ 顔で叩き殺す。 人間は最愛の者とこそ対決しなければならない。統一を欲するからだ。 中途半端という子供の誕生を嫌うからだ。 * 秋日 あいつの黄色いシャツが 午後の港を、笑いながらころげて逃げて行く。 サイレンが瓢箪状に空を這う秋の一日 倉庫の壁を塗っていた大工たち。 それから、シュークリームみたいに、 みんな、秋の陽に解けて行ってしまった。 * 演技で人を騙せると思ったら大間違いだ。 演技こそ所詮、お互いの障壁を越えられぬ人間同志を溶解する、唯一の薬品だ。 酩酊する船の上で嘔吐するから、その人間の船酔が知れるように、人間界と言う劇場で演伎してくれるから、役者だと知れる。 人を騙すには自然の如くあらねばならない。つまり純粋無垢だ。 * 秋の風鈴 夜道に、仕事を終えて 鳴き渡る 秋の風鈴。 ーお前は何をしてきたか。 私に問うのは、私の声 * 絵の中の時間・・・0から同時にー5と+5を計算した0を描くこと。 つまりは自画像が一番「時間」を現した絵になる。 文学も、否、あらゆる芸術はしかるべき。 * 二月六日 僕は友人の彼女に惚れてしまったのかも知れない。 夜、その女から借りたレコードを聴く。 アズナブールの「イザベル」。 男が鏡に向かって化粧する気持ちが判ったような気がした。 * 絹の唇に何をお返ししましょうか。 僕の時計は永久に正午を指している。 只、一秒足らずの前後がサンドイッチしている時計だ。 * 小鳥と寝台(女の出題に対する即興詩) 春 その白い砂浜に、薄紫の花模様を落す空中の寝台。 波間を諒めて、小鳥は林の中に消える。 夏 夏の寝台は倦怠と空白。 小鳥は赤く燗れた夕焼け空を、東から西、黒い絹糸の一瞬の艶を曳く。 秋 白陶のカップに残した琥珀色した二筋の珈琲が、二人の思い出を燻らせる。 小鳥は金色の枯葉に寄せて、その疲れた羽根を畳む。 冬 森の中に置き忘すれ去られた寝台の上、 小鳥が赤き実を啄んだ口ばしを天に向けて、 静かに息を引き取る時、 野山に白く初雪はレエス模様の沈黙を語る。 * 二十二歳。僕は人を軽蔑することで、退屈な人生の日常を支えている。 軽蔑が又、どんなに自分にとって苦い毒薬であり、甘味な良薬であったろう。 ・・・こう考えて、フト、僕は自分のエゴイズムと孤独に遭遇する。 僕は自己の孤独を思う時、自分が神に近付いたような錯覚をする。 全てのものが独占できるからだ。 孤独こそ王位の冠だ。 では、こうだと言うのか。孤独とは誰よりも所有するものが豊富に満たされた状態だと。 * ビルの谷間に蜜柑の一滴落ちて夕焼けが生まれた日、一番気取り屋だったのは乞食。 垢でひび割れた首筋の痛さは何とも素敵じゃないか。 * 夜、渋谷の雑踏を歩いていたら、若いひと組のしあわせそうな恋人カップルが目についた。 少女の足は醜いほどのビッコだった。 僕は人間の心の奥底まで歌い上げようとする詩人から隣の小母さんまで、 その悲しみは存外彼等の不幸と近くに有ると信じて疑わない。 しかし、この恋人達の喜びは何人にも推し量れない喜びがあるのであろうと思った。 人間は自己の裡の悲しみを他人の悲しみと尺度で計ろうとする。 愚の愚の愚だ。悲しみを共有するなんて簡単だ。 人間が人間商売を止めぬ間は。喜びを共有することが出来ないのだ。 不幸にも人間には。 * 立ち昇る煙草の煙りが 剥がれかかった、黄色い女の笑いを吸い取って 港の泥水に、吐き捨てられるといい ザラアメのように俺の脳髄を波打つ、この苛立たしさを 俺は都会の片隅で聴くに堪えない ピアノの転がる音が邪魔だ 迸る俺の心を なお、急げと言うのか 鳴呼、俺は夢見る 菜の花の絨毯に墜ちる 青いもの達の叫び声 小川の縞に縫い取られた 光の花々を。 * 単純さとは・・・複雑に複雑な岐路を巡り、 あたかも茨の道を抜け出た時に出会う静かな泉の水面 の様でなくてはならない。 何はともあれ、至純な形式とは飾りのない単一な美を現す。 * 僕は僕の心象イメージを彼女に語ってきかせる。 彼女の裡に宿る心象イメージと僕は同化する。 美は愛することの陶酔の中に居るのかも知れない。 即ち、僕達が美を発見したと思う時、そこには愛の陶酔があるかも知れない。 * 十月下旬の薬師寺の境内に座って、薄暮の中に僕は独り煙草を吹かす。 * 男女間の奴隷とは、罪悪感を抱いた方の人間の自由への渇望に他ならない。 だが奴隷が自由を得たと思う時、人は実は偽善を得ているのだ。 バターと醤油で炒めた玉葱の 秋の香に浸って 四畳半男と女は 赤茶けた罪を呑む。 中心を見つけようとする 女の瞳に映った 傾斜した電球コード やくざな観念にどっぷりした 俺の前には 去年の正月に買ったひょっとこ面が 取り澄まして、正しく 壁を睨んでいる。 こんな狭い部屋なのに 果ては遠い潮騒の響きから ここは鉄工所の溶鉱炉の音まで あたかも罪が、そのように 遠くから聴こえ、近くで聴こえ 私のお前と、お前の私という鎖が生んだ結び目が 軋み、息苦しく ダーク・グリーンの秋の空気に充満する。 房総西線 私の心の遠景に、夕陽はあたり また、汽車は淋しく走り出す。 錆びた鉄路に、薔薇色雲の鐘は鳴り、 トタン屋根の町に、飛んでゆく。 風吹きパタパタ 彼岸の泥船に 菜の花ユラユラ 静かに揺れて さて光は温暖に降り注ぎ 子供達の振る手は柿色に 今は、白鷺の羽根を追う。 私にはこの西線沿いは、ブリキの音がする みんな、玩具の兵隊だ。 茶色く、カランコロン、カランコロン、 見れば、田畑は静かに 水の空缶に空を入れている。 |
|
|